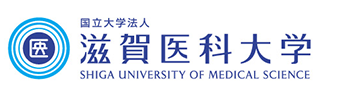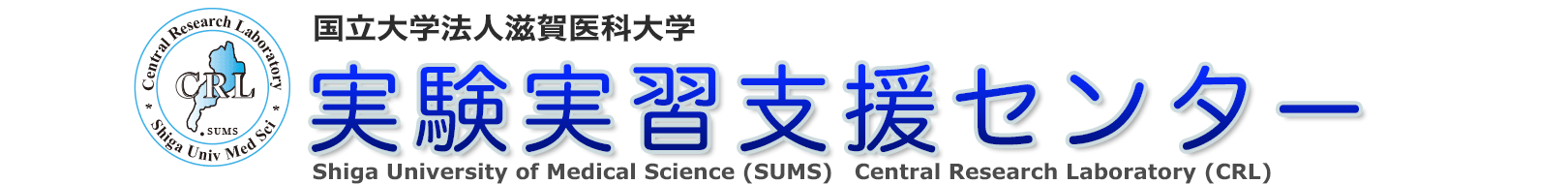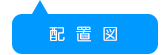
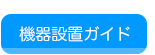
プロテインシーケンサーについて
プロテインシーケンサーとは
新たに得られたタンパク質やペプチドの高次機能や生理活性を明らかにしようとするとき、それらの一次構造(アミノ酸の配列順序)を明らかにするという仕事がかなり重要な位置を占めます。ペプチドやタンパク質のアミノ酸配列順序を決定するには、ペプチドやタンパク質を適当な長さの断片にしてからそれぞれを精製し、N末端およびC末端からアミノ酸配列を順次決めて行き、オーバーラップ法、さらには、S−S結合の位置決定等を経て一次構造が決定されますますが、とにかく大変な労力と時間を必要とします。現在ではDNAの塩基配列からタンパク質の一次構造を推定する方法が数多く報告されるようになりました。しかしながら、タンパク質の一次構造を決定するという仕事は依然として重要テーマであることに変わりはありません。そしてこの目的を達成するのに大きく寄与しているのがエドマン分解法に基づく自動化プロテインシーケンサーです。
エドマン分解法について
1949年 P.Eedmanによって見出された反応で、タンパク質やペプチドにフェニルイソチオシアネート(PITC)を反応させてN末端アミノ酸のアミノ基をフェニルチオカルバミル誘導体(PTCペプチド)に変え、これを酸処理することによってN末端アミノ酸がアニリノチアゾリノン誘導体(ATZアミノ酸)として切断除去されN末端アミノ酸が1残基除かれたペプチドが得られます。ATZアミノ酸はフェニルチオヒダントインアミノ酸(PTHアミノ酸)に変換してHPLCにて同定することが出来ます。
この反応を繰り返すことによってタンパク質やペプチドのアミノ基末端から順次アミノ酸を同定することが出来ることから、1967年にはEdman, Beggらによってこの反応を自動的に行うことの出来る装置が考案されました。その後、改良が加えられ、今日では反応の一部を気相で行う高感度分析装置が一般的になっています。
センターに設置されています装置はパルスリキッド法という気相法の変法を採用した装置で、2〜3ピコモルで30残基程度の分析が可能です。
 前へ 前へ
|
先頭へ
|
Last Updated 2005/8/25