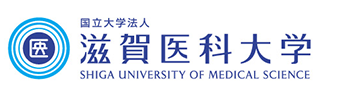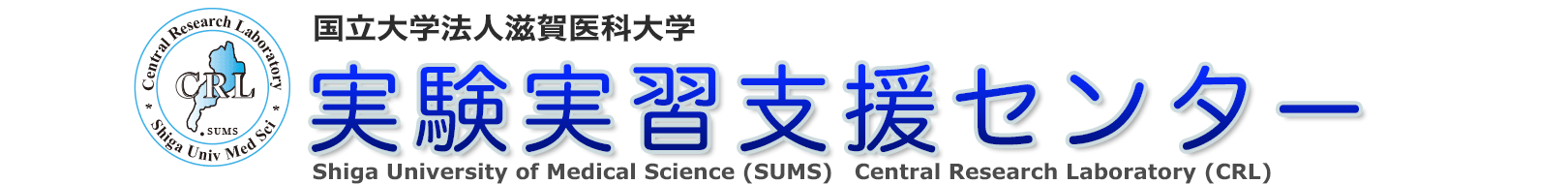摘出血管の張力変化に関する実験
岡村 富夫 薬理学講座
マグヌス装置を用いて摘出臓器の張力変化を調べる実験は古くから行われており、実験技術としては比較的簡単なため、多様な用途に応用されてきた。摘出血管を用いた実験についていえば、降圧薬の作用機序として心機能の抑制に依るのか血管拡張に依るのかを区別したければ、摘出心臓を用いたランゲンドルフ法と摘出血管を用いたマグヌス法を併用すれば直ちに答えがでるわけである。今でもこのような大づかみのスクリ−ニングに用いられることもしばしば見られる。例えば、ペプチド・ハンティングを行い、新しい構造の内因性ペプチドが見つかった場合には必ず試みられるし、循環器作用薬でなくても新薬の開発過程で必須の実験になっている。ただし、血管が拡張するか収縮するかを知るのは簡単でも、その詳細な機序を知るのは以外と難しい。その理由の一つは、摘出血管は摘出血管平滑筋と同一ではないからである。血管壁は内膜、中膜、外膜の3層構造を有している。1980年のFurchgott による内皮由来血管弛緩因子(EDRF, Endothelium-derived relaxing factor)の発見が契機となり、それまで単なる血液成分と平滑筋細胞を隔てるバリア−としての機能しか考えられていなかった血管内膜が、実は血中を流れる生体内物質の血管作用を瞬時に抑制したり、増強することにより積極的に血管平滑筋の緊張性調節に重要な役割を果たしていることが明らかにされた。このことは、多くの薬理学的な概念を変えた。その一つはそれまで血管拡張薬は血管平滑筋を直接拡張させると考えられてきたが、必ずしも直接作用であるとは限らなくなったことである。この点に関しては内皮除去標本を作製し、内皮正常標本と比較するという方法で多くの血管拡張薬が再検討された。もう一つは、EDRFの発見に用いられたアセチルコリンが、これまで血管以外の平滑筋を強く収縮させるのに、なぜ血管内に注入すると血管が強く拡張させるのかという疑問が氷解したことである。EDRFの発見以前には平滑筋には血管平滑筋と血管外平滑筋という2種類の機能的な概念があったが、必ずしもそう考える必要はなくなった。結論として、アセチルコリンの平滑筋に対する直接作用は収縮作用であり、その強さの程度が平滑筋の種類により異なるのであり、血管で観察される強力な弛緩作用は、アセチルコリンに反応して内皮細胞が産生した物質の強い拡張作用がアセチルコリンによる弱い直接の収縮作用を上まわったためと考えられる。さらにアセチルコリンが直接血管平滑筋を拡張させないという事実は、仮に血管壁にコリン作動性神経が分布し、機能しているとしても決してアドレナリン作動性神経と生理的な拮抗関係にないことを示している。ここで述べる血管支配神経の機能は、血管を生体から摘出した段階で自発的な活動は観察されなくなる。しかし、電気的あるいは薬物を用いて化学的に血管外膜に存在する神経終末を刺激すれば、支配神経から遊離される神経伝達物質の機能あるいはそれに影響をおよぼす因子を調べることができる。すなわち、血管の緊張性に影響を与える因子を、中膜に存在する平滑筋の張力変化により解析するのであるが、内膜に存在する内皮細胞および外膜に存在する支配神経の機能に与える影響を検討し、それらの総和として理解して始めて生体内での血管作用を類推できることになる。
これまでは血管について述べてきたが、同様の実験を気管、消化管、瞳孔括約筋、尿管、胆管、輸精管、膀胱や子宮平滑筋などで行うことが可能である。もちろん、摘出した各臓器の組織学的な構造をよく理解したうえで実験をはじめる必要があるのは言うまでもないが、実験技術としては大きな差はない。しかし、標本の作製、再現性のある成績、成績の分析には適当な技術と経験が必要となる。今回は摘出血管を材料にし、その講義と実習を行う予定である。
可能なプロトコ−ル:薬物間の比較、動物種差、雌雄差、血管部位差、血管サイズの比較、動静脈差、年齢差、病態モデル動物との比較 など
 前へ 前へ
|
先頭へ
|
Last Updated 2005/8/18