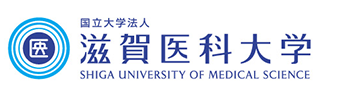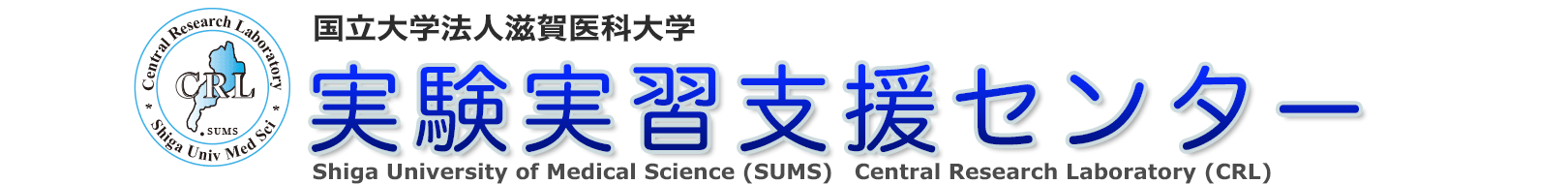Seeing is believing(免疫組織化学による形態観察)
木村 宏 Hiroshi KIMURA (システム脳機能・教授)
免疫組織化学、抗体、細胞形態、染色
はじめに
組織や細胞の形態を顕微鏡で調べるのは、それら構造のもつ機能を考える大きなヒントになるが、組織・細胞に含まれる化学物質を色づけて同時に眺められればさらによい。化学物質の色づけ方法にはいくつかあるが、たとえばアミノ酸数個の配列を特異的に検出できる抗体の特性を利用し、生体内の(抗原性)物質を光顕あるいは電顕レベルで観察する方法が免疫組織(細胞)化学である。この方法を使いこなす基本的な考え方は、1)組織細胞のカタチ(構築)をできるだけ保ちながら、2)その中の抗原の局在を正確かつ安定して検出するよう工夫を払うことである。しかし、これら2点は実際的に二律背反の性格をもち、腕をふるうポイントである。
免疫組織化学の普及はめざましく、非常に多種の抗体や染色キットが市販され、形態学を専門としない医学を含めた広い生物学分野の研究者によって活用されている。しかし、染色結果やその解釈に誤りがあると、せっかくの研究努力もフイになる。ここでは、免疫組織化学の原理を概略したあと、実用的な方法を具体的に紹介し、注意点を述べる。正しい技術によって染まりあがった標本を顕微鏡で眺めると、抽象的あるいは概念的な知識や考えがたちどころに具象化し、顔かたち(形態)から様々な役目(機能)が類推され、日なが一日飽きることなく、研究の夢を楽しめる。まさに、一目瞭然で、百聞は一見に如かずが実感されよう。
- 免疫組織化学の原理
組織や細胞に含まれる抗原物質をそれに対する特異抗体と反応させ、抗原抗体反応による結合抗体の有無から抗原の存在を知る、というのが免疫組織化学の原理である。この際、抗体を予め可視化マーカーで標識しておくのが標識抗体法であるが、最近は組織に結合した抗体の存在を増幅して検出できる非標識抗体法が考案され、その応用範囲の広いこともあって急速に普及している。
- 組織固定
免疫組織化学の目的の一つは組織や細胞の形態を観察することであるから、死後に生じる自己融解をふせぎ、その構築をできるだけあるがままに保存することが最も重要である。しかし、固定液の多くは抗原を化学修飾する傾向があるので抗原性の低下を招くので、その対策の具体例として、潅流固定法と浸漬固定法を紹介する。
- 固定液の組成
固定処理の操作は免疫組織化学の鍵を握るもので、うまく行けば目的の半ばが達成されたと言えるが、逆にこの段階に不都合があれば以降の免疫染色をいくら頑張ってもダメといっても良いほど重要である。固定操作のテクニックが適当であったかどうかは経験則により体得するか、必ず染まると信頼されている抗体を用いて練習することが重要である。また固定液の選択も、研究者によって、あるいは目的の抗原物質とそれに対応する抗体によって異なる。いずれにしても、抗原性の低下を出来るだけ避けるために低温で組織を固定することがコツである。
- 切片作成
切片の作成は、一般の光顕標本と同様にパラフィン包埋してからミクロトームで作成してもよいし、あるいは組織ブロックを凍結してクリオスタット切片としてもよい。クリオスタット切片作成のコツは、組織ブロックをサイホン式ボンベから噴出させた炭酸ガスで組織を急速に固定することが第一である。クリオスタット庫内での凍結は巨大な氷結晶を生じやすく、顕微鏡で観察すると小さな孔が無数にあいてみえる。もう一つのコツは、凍結したブロックや切片をクリオスタット庫内に不必要に長くおかないことである。
- 切片の前処置
免疫組織化学の染色操作に移る前に、切片を前処置しておくと染色結果が良くなることがある。その一つは非特異的なバックグラウンド染色を避けることであるが、もう一つは酵素処理などにより抗体の浸透性を良くしようというものである。このほか、抗体の浸透を良くするもう一つの一般的な方法として、PBSにトリトンX-100(0.3%)を加えた液で切片を4日間ほど処理すると、うまく行くことが多い。ただし、トリトンは電顕免疫組織化学には不適である。
- 第一抗体との反応(浮遊法と貼付法)
いよいよ免疫組織化学の染色であるが、第一抗体と反応させる切片は液に浮遊した状態で行う(浮遊法)かまたはスライドグラスに貼り付けた状態で行うか(貼付法)の2種がある。浮遊法で用いる抗体の濃度は貼付法の場合より約100-1000倍希釈したもので十分である。反応時間は3-7日間と長いほど、また低温(4℃)で行うほど、バックグラウンドの低い優れた結果が得られることがしばしばである。要するに、薄い抗体濃度で長時間、低温でゆっくりと反応させるのがよい。抗体の至適濃度は用いる抗体の力価(抗体価)によるので、一般的な目安はない。たとえば、数種類の倍進希釈した抗体液を切片と反応させて、染色結果から経験的に決定する。
- 第2抗体から発色反応まで
組織切片中の抗原と第一抗体はすでに結合しているので、反応時間は2時間を越える必要はなく、室温で十分である。両方の方法とも、最終反応はペルオキシダーゼの酵素活性をジアミノベンジジンによって可視化するが、ニッケル増強すると感度が向上する。
- 染色の特異性(信頼性)検討ーポジコンとネガコン
はじめて免疫組織化学の染色を行うときには、あらかじめ検出しようとする抗原が必ず含まれている組織または細胞(ポジティブコントロール)と存在しないことが確認されている組織または細胞(ネガティブコントロール)を同時に染色し、結果を比較すれば、染色の正当性を判定するのに役立つ。
- おわりに
免疫組織化学は豊富な種類の抗体が手に入るようになり、技法も簡便化され、さらに高感度な検出が可能になりつつある。だからといって、マニュアルどおりに操作すれば信用できる結果が得られるとは限らない。すべての操作段階が誤りなく至適条件であるかどうか、邪魔くさいようでも一つ一つ自分の目で確かめる慎重さが求められる。かなり長いステップと沢山の要因が複雑にからまるようにみえるが、各ステップの成否は確かめられることを念頭に実験を行うことは、結果的に実り多いと思われる。
参考文献
- 木村 宏:活性ペプチドとくに神経系の伝達物質の検出、組織細胞化学1982、PP.155-165.
- 木村 宏:抗体の作成と特異性検討法、組織細胞化学1988、PP. 127-142.
- 木村 宏:抗体の上手な使い方、組織細胞化学1993、PP. 15-22.
- 木村 宏:免疫組織化学による光顕観察、組織細胞化学1997、PP. 201-204.
Copyright (C) Central Research Laboratory. All right reserved.since 1996/2/1
Last Updated 2005/8/8
 前へ
前へ