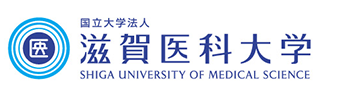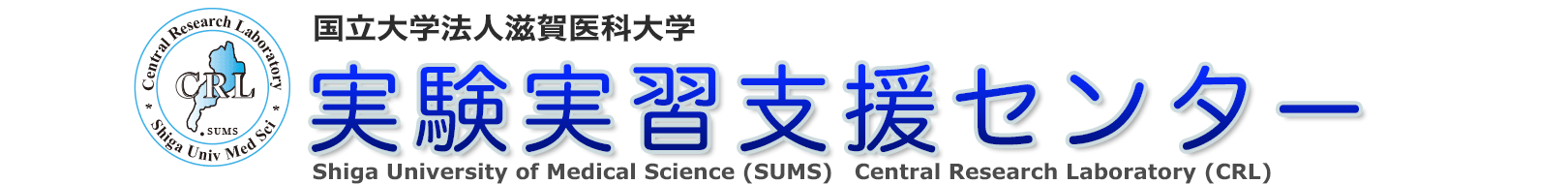FISHの原理と間期核細胞遺伝学
杉原 洋行 病理学第一講座
蛍光in situ hybridization (FISH) は染色体解析に多用されている。この講習会では、FISHシグナルの検出原理だけでなく、可視化したシグナルを如何にカウントするかと言う問題にも触れたい。
1. 間期核細胞遺伝学と反復DNA配列
蛍光in situ hybridization (FISH)によって、特定の染色体の特定の部分に対応する染色体DNAを、分裂期だけでなく間期核でも簡便に可視化できるようになった。
probeは2本鎖のgenomic DNAそのものをcloningしたものである。cDNAは高々数Kbpであるので、FISHに用いても検出率が低い。ただ、検索の目的が遺伝子のorderingの様な場合は、ほとんどすべての核でシグナルが検出される必要がなく、再現性を確認できる程度に検出できればよいので、cDNAでも使用可能な場合がある。
一方、核のスメアや組織切片でシグナル数の分布を見る場合には、ほとんどの核でシグナルが十分検出されていなければならないので、そのような場合は、可視化する染色体DNAのtargetの多くは反復配列である。反復配列はヒトゲノムの30ー40%を占め、その1/3がtandem repeat、2/3がAluの様なinterspersed repeatである。FISHの標的は前者である。単位配列をプラスミドでクローニングした、2本鎖genomic DNAをprobeとして使うことが多い。tandem repeatにはセントロメア近傍に見られるもの(古典的サテライトおよびアルファサテライトDNA)と、ゲノム内に散在するもの(ミニサテライト)とがある。前者は染色体特異的なprobeとして、後者は染色体のlocusに特異的なprobeとして使われる。同じくlocus-specific probeとして使えるsingle copy probeでは、FISHで十分見えるためには約40 Kbp以上のサイズが必要である。そのためにはprobeはcosmidやYACでクローニングする必要がある。
また、cell sorterで分離した特定の染色体のlibrary DNAをprobeに使うと、特定の染色体全体をpaintすることができる。このようなprobeは染色体転座の研究や、間期核での染色体構造の研究などに有用である。
通常、probe DNAとtarget DNAを加熱して変性(単鎖化)させて混ぜ合わせ、それがreannealする際に同じsequenceのDNAどうしが分子雑種をつくるという原理を使っている。probeをbiotinやdigoxygeninで標識したり、直接蛍光色素で標識することによって、可視化するのである。標識にはnick translationが用いられる。その際、DNaseの濃度を調節して、(probeとしてcloningされたDNAのサイズは様々であるが、)最終的には、標識されたDNAが300-500 bp程度の断片になるように調整する。
この方法によって、ひとつの染色体DNAは分裂期だけでなく間期でもかたまって存在すること、そして分裂期と間期で同様のシグナルが観察できることが明らかになった。これにより、古典的なbanding法では分裂期核に限られていた染色体分析の対象が、非増殖細胞も含めた、すべての核にひろがったのである。この新たな分野を間期核細胞遺伝学(interphase cytogenetics)という。
2. 抽出DNAのmicrosatellite解析と単離細胞のFISHの対比
FISHでは、標的DNAを直視下に見るという意味で、抽出DNAよりも直接的な情報が得られる。すなわち、腫瘍組織の抽出DNAには必然的に正常細胞が混在してくる。microsatelliteを用いたLOH解析では、これが常に問題になり、間質成分の多い場合は解析不能となる。FISHの場合は、個々の核で染色体のコピー数がわかるので、間質成分の多い腫瘍でも、腫瘍細胞のみの情報を得ることができる。ただ、細胞を単離してしまうと正常かどうかの判定が難しくなる。このため、複数の染色体DNA probeで同時に正常パタンを示すものを正常と見なすなどの方法がとられる。これらの点を、乳癌症例を用いてindependentに行った、16番染色体長腕のLOH解析とFISH解析を対比しながら具体的に説明したい。
3. 組織切片でのFISH
間質細胞の同定は、組織切片で直接FISHを行う方が容易である。また、細胞単離法では、単離過程で大型核が失われやすい傾向があり、多少とも細胞構成が変化することは避けられない。FISHを切片で直接行うことにより、細胞構成や位置情報を保ったままin situの染色体情報を得ることができる。
ただその際、核の切断が必然的に起こるので、10-20 μmの厚切り切片で、切断されていない核を探す必要がある。これを行うことは、通常の蛍光顕微鏡では不可能で、染色体シグナルを組織切片内で解析するためには次項で述べる共焦点レーザ走査顕微鏡(CLSM)による顕微鏡トモグラフィの手法が必須である。
また、シグナルの空間分布を見るためには、ほとんどの核でシグナルを検出する必要があることである。シグナルのunderestimationの原因の一つは、probeの浸透不良である。私たちは主として凍結切片(1% formalin/PBS 20 min固定)を用いているが、特に消化などの前処理は要しない。AMeX包埋切片でも同様である。通常のformalin固定パラフィン包埋切片では、かなり強い前処理を必要とする。また、浸透性はbiotin標識プローブとdigoxigenin標識probeで異なる。切片の前処置については、まだまだ改善の余地がある。また、シグナルの検出率の高い(大きなシグナルの得られる)プローブを選択することも重要である。
4. 顕微鏡トモグラフィとは
実際に組織を薄切することなく、光学的な連続断層像の得られる顕微鏡トモグラフィは、共焦点レーザ走査顕微鏡(confocal laser scanning microscope, CLSM)によってはじめて可能になった。光学的な断層像を得るためには、焦点面から来る光のみを検出する必要がある。このために共焦点系を利用する。共焦点系は、対物レンズに対して光源と共役の位置に検出器を配置したもので、実際は光源から出る励起光と検出器に入射する蛍光を分けるために、ダイクロイックミラーが使われている。最も重要な点は、共焦点系の光源および検出器と対物レンズとの間にピンホールを置くことによって、焦点面以外からの迷光を遮断することで、これによって焦点面から来る光のみを捉えることができる。ただ、光源はピンホールを通して点光源となるので、焦点面(x-y面)全体の断層像を見るためにはレーザ光をミラーで振って標本上を走査しなければならない。また連続断層像を得るために、ステージ駆動装置で焦点面を(z軸方向に)小刻みに移動させる。実際には更に、特異的なシグナルを増強すると共にノイズを相殺させるために画像を繰り返し取り込んで加算したり、3次元再構築のためのステレオ像やx-z面での断層像を合成するデジタル画像処理の機能が必要である。
5. 染色体の総数のカウント
セントロメアの数は一般に染色体数に対応しているので、セントロメアの数を正確にカウントできれば、間期核でも染色体数(つまりploidy)を知ることができる。全染色体のセントロメアを可視化するには2つの方法がある。alphoid反復DNAのconsensus配列をFISHで検出する方法と、抗セントロメア抗体でセントロメアの蛋白抗原を検出する方法である。ヒトの場合のように多数のセントロメアシグナルをカウントする際には、2次元的な単離核のスメアよりも、切片内の立体的な核を使う方が有利になる。多数のシグナルを再現性よくカウントするためには、連続断層像(0.5μm間隔)を順番に並べて、ひとつのシグナルが何スライスに切れているのかをシグナルごとに確かめながらカウントする。
次項でのべる特定の染色体の数的異常を解析する場合も、染色体の総数(これはDNA定量によるploidyのデータでも代用できる)を押さえておくことがきわめて重要である。特定の染色体のシグナルがdisomyの場合、それが正常と言えるのはdiploidの場合である。もしploidyが(ゲノムの倍加を経た)aneuploidyであれば、disomyは欠失を反映している可能性がある。
6. 特定の染色体のカウント
特定の染色体のコピー数は、その染色体に特異的な反復DNAプローブでFISHを行った切片でカウントできる。FISHの染色ムラや欠損のある核でカウントすると容易にunderestimationが生じる。カウント結果が正しいかどうかを評価するために、隣接する厚切り切片から単離した細胞のスメアで平行してFISHを行い、カウント結果を常に比較する慎重さが必要である。切片を使う場合は細胞単離操作が不要であるが、切片でのカウントを決して簡便法と考えてはならない。切片では核が欠損しているかどうかを評価するのがかなり面倒である。また、前項で述べたように、シグナル数の評価にploidyのデータは必須であるが、ploidyを正確に決定するためには単離細胞によるflow cytometryまたは顕微測光が必要である。このように、単離細胞と切片のデータは互いに相補的で、常に対比しなければならない。
7. シグナルサイズの多型の検出
常染色体では1番, 9番, 16番のセントロメア領域の反復配列は、alphoid DNAの他に別の反復配列(Satellite I-III)に富み、その反復数に個人差がかなりある。これは染色体分析でCバンド多型として知られていたもので、FISHでもこれらの染色体が父親由来か母親由来かによって、反復数に対応してシグナルサイズが異なることがしばしばある。その場合、シグナルが何枚のスライスに切れているかを比べ、最も大きなシグナルを含むスライスでのシグナルの大きさを考慮して大きさを比較する。
8. 染色体の構造異常の検出
組織切片で構造異常の解析のできるprobeのある染色体は、今のところ1番染色体の短腕に限られる。この1p36部位に、40 bpの単位配列が約7000回反復するVNTR(D1Z2)が存在する。このような大きな、組織切片でも容易に可視化できるVNTRは、今の所、ここだけにしか知られていない。このD1Z2をbiotin標識し、1番のセントロメアprobeをdigoxygeninで標識してFISHを行い、DAPIで核を染色する。DAPIの蛍光をCLSMで見るためには、紫外光で励起するための大型のアルゴンレーザが必要である。紫外光と可視光を同時に使う場合には色収差の問題が避けられないが、この点についても解決方法を考察したい。
9. 染色体異常の組織内mapping
組織切片でのカウントの最大の利点は、あるシグナル数をもつ細胞が空間的にどの様に分布しているのかがわかることである。まず、切片の厚みのちょうどまん中のconfocal imageを写真に撮り、その中に含まれる核の一つ一つについて、切れていないかどうか、連続断層像を見ながら判定する。そして切れていない核でシグナル数と個々のシグナルのサイズを記録する。これはかなり面倒ではあるが、この方法でしか得られないデータが得られるのである。
倍数体が散在性にみられる場合は、分裂異常などによって生じた可能性が高い。倍数体細胞が小さな集団として見られることも多いが、このような場合は、ある程度増殖能をもってサブクローンを形成していると考えられる。これらが小集団にとどまっていることは、これらの集団がまだ十分なgrowth advantageを得ておらず、生じては消えて行く状況を反映しているとも考えられる。このようなものの中から、更に染色体異常が付加されてaneuploidyが生じるのであろう。Cバンド多型がある場合、disomy細胞(●・)と共存しているtetrasomy細胞は4倍体のパタン(●●・・)となるが、aneusomy細胞の中に混在するtetrasomy細胞は●・・・などのパタンをとることが多く、これらはゲノムの倍加後更に不分離を繰り返して生じたことがわかる。
10. まとめ
染色体情報を得るには、比較的最近まで古典的な、単離された分裂像の伸展標本を用いるbanding法が唯一の方法であった。FISHの発達により、これまでmetaphaseに限られていた検索対象が非増殖細胞も含むinterphaseに広がり、さらにCLSMを使うことにより、材料が単離細胞のスメアからin situの組織切片に広がった。この方法を使えば、顕微鏡的に発見される微小癌にまで染色体分析の対象が広がり、in vivoの癌の初期・早期では染色体のなかでDNAはどうなっているのかといった問題に詳細なアプローチができるであろう。組織切片で特定の染色体部分が“見える”in situ cytogeneticsの時代がこれから始まろうとしている。
[・プログラム]
 前へ 前へ
|
先頭へ
|
Last Updated 2005/8/17